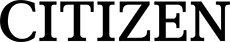オビラメの会では、5年にわたる調査で尻別川のイトウが絶滅の危機にあることがわかったことから、生息環境の保護による復活を断念。人工ふ化させて稚魚を放流し、もともと生息していた場所に再び定着させる「再導入」を目指すしかないとの判断に至った。
ここで重要なのが、復活を目指したのは、単なるイトウではなく「尻別川のイトウ」であること。放流するのは、尻別川で捕獲した野生のイトウから採卵・授精して人工ふ化させた、「尻別川固有の遺伝子を持つイトウの稚魚」でなければならないのだ。
さらに、イトウは一生に何度も産卵するが、受精卵の生存率が比較的低く、しかも成熟には4、5年から10年近くかかり世代交代に長期間を要する。このため、会では尻別イトウの再導入に挑むにあたり、「オビラメ復活30年計画」を2000年に策定。10年ごとの3つのステージに分け、第1ステージは稚魚の生産と再導入場所の選定、第2ステージは再導入によるイトウ繁殖拠点の再生、第3ステージは拠点を全流域に広げることを目標とした。