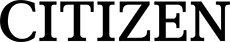昭和36年、地元の小学校の入学式当日、新入生が車にはねられる事故が発生。当時幅7メートルだった道路には、信号機はおろか横断歩道さえなかった。
地元で酒屋を営んでいた吉田さんはPTAではなかったが、地域の交通委員をしていたことから、輪番で始まった保護者による交通指導に応援で参加するようになった。しかし、そこで吉田さんが見たのはあまりにも危険な交通指導だった。「車の流れや運転感覚が分からないお母さん方が、急に車を止めようとして後続の車が追突しそうになるなど、危険な状況が頻発していました」。
これはいけないと感じた吉田さんは、警察署の交通課に1週間通い、旗の出し方や車の止め方の講習を受けた。「車を止めようと腕を前に出しても、ドライバーには手のひらしか見えませんから、まず真っすぐ上にあげなさいとか、交通指導に必要なことをいろいろ教えていただきました」
こうして、正しい交通指導を学んだ吉田さんは、保護者にも助言するようになり、自身も毎日交差点に立ち子どもたちの安全を見守るようになった。